
海外ドラマや映画から、またはSNSやニュースから垣間見える海外での暮らしに憧れることもありますよね。その国に住む同世代の女のコが考えていることをもっと知りたいなら、エッセイを読むのがオススメ。視点の違いもあれば、意外な共通点に気づくこともあって、視野を広げるきっかけになります。
『家にいるのに家に帰りたい』
著:クォン・ラビン 訳:桑畑優香/&books(辰巳出版)
まずは、韓国からのエッセイをご紹介。ここ数年、韓国の若い世代の著者によるエッセイが、続々と日本語に翻訳されて、韓国ドラマやK-POP同様に、日本の女性たちの心をガッチリ掴んでいる様子。
著者のクォン・ラビンは、1994年生まれ。この本はラビンのデビュー作で、BTSのVも読んだと話題に。心が弱っているときに、優しく染み込んでいく言葉たちがいっぱいで、ひとつひとつのエッセイを読むごとに癒やされていきます。押し付けがましさは一切なく、それぞれの気持ちを尊重したいというところは、韓国の同世代にも共通するのかもしれません。また、固定観念から解放されてきているところも、日本のsweet世代との共通点かも。この本でもLGBT、障がい、貧困など、マイノリティも包み込む社会を目指す、彼女の理想が描かれています。でもあくまでも暑苦しくなく、さりげなく。
彼女自身の経験から書かれた恋愛についてのエッセイも、同じ状況にいる人の心に染み込んでいくはず。別れの悲しさと、また訪れる恋の温かさが感じられます。
 『ここじゃない世界に行きたかった』
『ここじゃない世界に行きたかった』
塩谷 舞/文藝春秋
次は、ニューヨークで暮らす日本人女性によるエッセイ。塩谷舞は1988年生まれ、大阪出身で、就職で上京したのち、アーティストである夫と一緒にニューヨークに行くことを決めます。そのときに彼女は29歳。
大阪の千里ニュータウンという平和な街で育った彼女が、ここではない場所に行きたいと思ってたどり着いたニューヨーク。家賃は高く、日本に比べて治安も悪く、カタコトの英語でなかなか友達もできず……とニューヨークでの生活はとても厳しく、日本にいて遠くから憧れの目線で見ていたのとは違うリアルを彼女も知ることに。そこで奮闘するなかで、家具や陶芸などに対する美意識でつながることのできた友人たちとのストーリーは、美が国籍や言語を超えていく実感があって、心を動かされるものです。
また、昨年以来のコロナ禍でのニューヨークの状況や、BLM(Black Lives Matter)問題を現地でどう感じたのか、バイデンvsトランプの大統領選がニューヨークでどういう盛り上がりを見せていたのかなどなど、太平洋対岸の日本ではなかなか分からない、肌で感じるアメリカを彼女を通して知れる一冊です。
『パリと生きる女たち』
著:ジャンヌ・ダマス、ローレン・バスティード 訳:徳山素子/アノニマ・スタジオ
ジェーン・バーキンの再来とも言われ、自身が運営するブランド「Rouje(ルージュ)」が日本でも大人気のジャンヌ・ダマスと、フランス版『ELLE』の元編集者でフェミニストでジャーナリストのローレン・バスティードが、「パリジェンヌとは?」というテーマでパリに住む様々な20人の女性たちを取材した一冊。靴デザイナー、ナイトクラブのPR、元エディター、映画監督、政治活動家など、みんな個性的で少しも似ていない。
ここで紹介されるパリジェンヌたちは、白人だけではなく、アフリカ系やアジア系も含まれるし、年齢も14歳から70歳と幅広く、パリジェンヌという概念を更新するものなのです。
それぞれの個性豊かな女性を紹介する文章が素晴らしいのはもちろん、掲載されている写真も1枚1枚グッときてしまいます。彼女たちの生活が浮かび上がってくるような部屋の小物や、洋服、そして自然体な表情。
それぞれの女性が考えていることを読むと、昔から変わらないパリジェンヌのよさと、そして今らしく更新されたパリジェンヌのスタイルとが見えてくるような気がします。
美味しいブーランジェリーやワインセラー、パリジェンヌの行動学など、幕間みたいなちょっとしたコラムもエスプリがきいていて、さすがパリ!
●千田あすか
編集・ライター。シンガポール在住経験からのシンガポール情報や、書評などのカルチャー情報をお届けします。インスタグラム @aska_chida


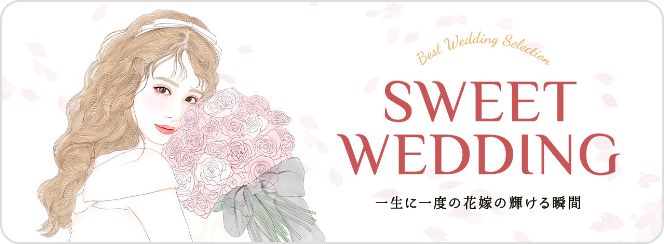


 『ここじゃない世界に行きたかった』
『ここじゃない世界に行きたかった』









 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>















